松浦市協働によるまちづくり指針
本市は、松浦市総合計画において「協働によるまちづくり」を推進しています。
「協働によるまちづくり」は、総合計画に掲げた将来像を実現するための方法です。
本指針では、「協働によるまちづくり」に関する一定のルールや考え方を示しています。
協働に取り組む上での道しるべとなり、市民と行政がお互いに共有する「手引き」として活用していただければ幸いです。

2030年の松浦市みんなの想い未来地図
なぜ、「協働によるまちづくり」が必要なの?
これまで私たちは、身近な問題を家族や隣近所、あるいは自治会などの多様なコミュニティが関わることで解決してきました。
しかし、現代の地域社会では少子高齢化、過疎化、防災、環境保護など解決しづらい複雑な問題が発生しています。
また、個人の価値観の多様化や地域社会を取り巻く環境が変化しており、都市部ほどではありませんが、
地域コミュニティの希薄化も進んでいます。
一方で、多様化・複雑化したニーズに対して、行政の活動領域も変化していますが、緊縮財政や人員削減などの要因もあり、
行政だけでは解決できない課題も出てきています。
地域社会の中で取り組んでいく分野や活動は、時代とともに変化していきます。
地域を取り巻く環境の変化を踏まえて、10年後、20年後の地域の姿を想像して、住み続けたいと思えるまちを作ることが大切です。
「協働」とは?
本市が目指している「協働」とは
「市民と行政が対等・平等な立場で、自分たちのまちの将来や課題等について、
ともに考え、学び、行動する」こととしています。
「自分たちの住むまちは、自分たちで創る」という思いで、
様々な立場を超えて話し合いながら、
課題解決などに取り組むことがまさに私たちが目指しているまちづくりの姿です。

「協働」で取り組む活動とは?

地域でできることは地域の自主性や主体性に任せ、
地域団体や企業など民間に任せた方が良いものは民間に任せる。
法の義務付けがあるものや市民生活の安全・安心を守るものなど行政が担うべき分野は、
行政がしっかりと取り組みます。
そして、市民と行政がお互いに補完・協力し合いながら進めた方がいいものは
協働によって活動するという、新しいまちづくりの形を作っていく必要があります。
「協働」を進めるための基本的な考え方

「協働によるまちづくり」を推進するために、この6つを基本原則として定め、活動に取り組む際に大切な考え方とします。
「協働」を担う主体となる「まちづくり運営協議会」

まちづくり運営協議会は、おおよそ小学校区単位で自治会を中核として、
青少年健全育成協議会、老人クラブ、PTA、民生委員、児童委員など
地域内で活動する各種団体で構成するものです。
組織構成は地域の実情に合わせて柔軟に決めていきます。
地域毎に直面する課題の内容や重みが異なることから、
各地域のまちづくり運営協議会が地域の実情に合った個別のまちづくり計画を策定し、
各種活動に取り組んでいきます。
「まちづくり運営協議会」の役割は、「地域を経営する」ことと言えます。
経営とは、地域の様々な人や組織、地域資源、お金などを組み合わせ、最も住みやすい地域を実現していくことです。
協働によるまちづくりを推進する中では、
行政またはまちづくり運営協議会がそれぞれ主体的に取り組む活動もあれば、一緒に取り組む活動もあります。
協働によるまちづくりで目指すまち

「協働によるまちづくり」を通じて、本市は(1)学び育てるまち、(2)誇れるまち、(3)仕事をつくるまち、(4)未来へ続くまち、(5)安心、幸せのまち、(6)皆でチャレンジするまちの6つの将来像の実現を目指しています。
「協働によるまちづくり指針」の改訂
令和5年6月改訂版の策定
まちづくり運営協議会の地域の範囲の変更及び協議会設立までの流れを追加し、併せて文言等の訂正等を行いました。
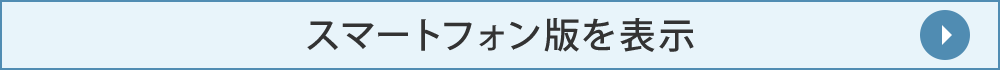









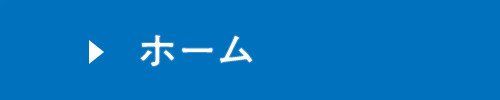

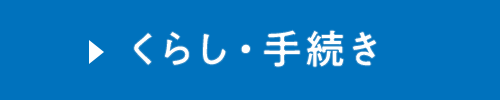




更新日:2022年03月19日