百手講(ももてこう)
市指定無形民俗文化財 平成21年9月30日指定

志佐町庄野地区の氏神である王嶋神社に古くから伝わる百手講は、市内でも歴史のある伝統行事のひとつである。毎年、新春の1月8日庄野地区の人々が、庄野公民館に集まり、直径約50センチメートルの桟俵の的と、長さ150センチメートルのイタビの木で作った弓と竹の矢を神前に供え、御祓いのあと、地区より射手に選ばれた2人が狩衣・烏帽子姿に身を固め、神社の境内に設置した約10メートル先の的に向かって矢を射る神事である。矢が的に当たれば当たるほどその年は豊作になるといわれている。
大宝律令(701年制定)によって「国郡里制」が施行され、50戸の集落をもって里制にした当時の行政制度で、50人一組となって狩りをした際、家長の両手を集めると、ちょうど百本になることから、「百手講」とよばれ、獲物の量で、その年の豊凶を占ったのが始まりだと伝えられている。いまでは、集落の相談ごとや話し合いの場を称して「百手講」と呼ぶようになっている。
この百手講は、古くからの里制制度が今日まで継承されている例で、矢を射て五穀豊穣を祈願する長い伝統をもつ全国的にも珍しい行事である。
百手講は、五島では「的射」、諫早では「百手まつり」と、全国的には「歩射まつり」や「射礼」といわれている。

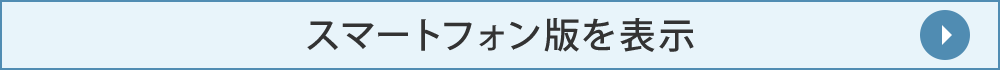









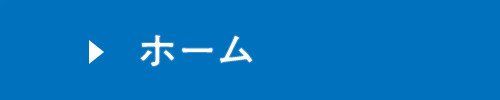

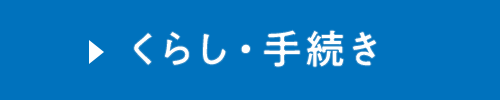




更新日:2019年04月01日